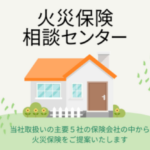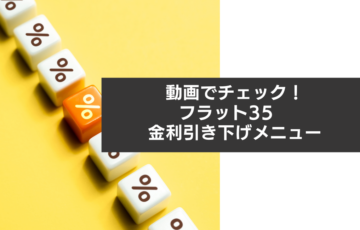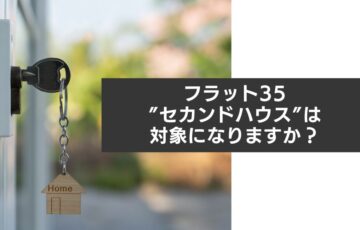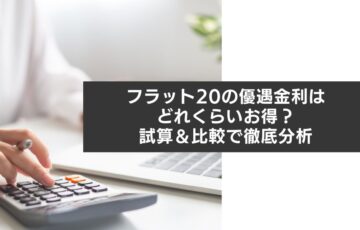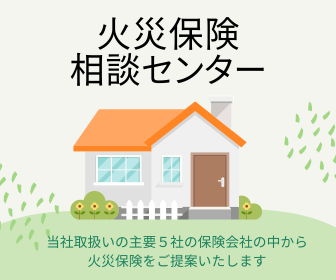住宅ローンには大きく分けて次の2つの系統があります。
都市銀行、地方銀行、ネット銀行、労働金庫などの民間金融機関によるもの。
もう一つは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)による国の政策の後押しを受けた公的な長期間固定金利ローン「フラット35」です。
民間金融機関の住宅ローンのタイプ
民間金融機関による融資には「全期間固定金利型」「固定期間選択型」「変動金利型」があります。
全期間固定金利型
住宅ローンを借りている間の金利が変動しないタイプで、借入時に金利と総返済額が決定します。
固定期間選択型
3年間や5年間等、一定期間を固定金利に設定することが出来ます。期間が終了した時点で変動金利型にするか、再度固定金利型にするか選択する必要がありますが、その際はその時点の金利が反映されます。
変動金利型
その名の通り一定期間ごとに金利が変動します。半年ごとに金利が見直される商品が一般的です。
これらの民間金融機関による住宅ローンの場合、全期間固定型よりは固定期間選択型や変動金利型の方が金利は低く設定されています。また固定期間が短ければ短いほど金利が低くなっています。
民間金融機関の「審査金利」とは
住宅ローンの借入額を計算するにあたって、店頭表示金利の他に、銀行内部にはもう一つ「審査金利」というものがあります。
金融機関によってこの審査金利は異なりますが概ね3%/年程度となっています。
民間金融機関で変動金利0.875%の住宅ローンの借入申込をしても、銀行内では3%程度の金利として貸出限度の計算をします。
例えば年収450万円の方が35年ローンで借入申込をした場合、審査金利3%で借入可能額は3,410万円程度となります。
民間金融機関では実際に融資をする金利ではなく、金利変動リスクを鑑みた審査用の金利で査定をするため借入可能額はある程度抑えられた金額となります。
フラット35の「審査金利」は各月の実行金利が基準
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の長期固定金利ローン【フラット35】の場合、民間金融機関のように、店頭金利と審査金利が異なることは無く、各月に公表される実行金利がそのまま審査金利となります。
また、審査基準となる返済比率計算も公表されていますので、借入可能額の計算も明確です。
年収450万円の方が35年ローンで借入申込をした場合、当月の実行金利が1.8%とすると、審査金利も1.8%となり借入可能額は4,087万円となります。
この様に同じ年収450万円の方の場合であっても、フラット35の方が民間金融機関の融資額よりも677万円程度融資可能額が多くなります。
条件比較のために民間金融機関とフラット35の両方に申込みをしてみて条件を比較することもお勧めします。

【フラット35全期間固定型住宅ローン借入金利情報】
詳しくはこちらをご覧ください(これより先は、住宅金融支援機構のウェブサイトに移動します。)(住宅金融支援機構フラット35金利情報)
そもそも「フラット35」って何?
フラット35は住宅金融支援機構が行う性能の高い住宅の普及を促すために国が後押しする公的な住宅ローンです。
(詳細は下記をご確認下さい)
申込要件等、主な内容は全国共通ですが商品を提供するのは民間の金融機関で、金利のタイプは全期間固定型のみとなります。フラット35の「35」は35年固定金利という意味で、最長35年間の長期固定金利の住宅ローンです。また、長期優良住宅の場合は、最長50年の【フラット50】、最長20年以内の【フラット20】が提供されており、それぞれ金利設定が異なります。
【フラット35】の金利は融資割合と借入期間で変わる
金利は資金計画総額の9割超融資と9割以下融資の2つに分かれていて、借入金額を9割以下にすると金利を低く抑えることができます。
フラット35で資金計画総額の100%を借入することもできますが、物件価格の9割以下の借入の場合と9割超の借入金利の差があるため、通常はフラット35の借入はを9割までに抑えるのが一般的です。
残りの1割は自己資金を用意するか、もしくは民間金融機関のローンを利用することもできます。
物件の1割について民間金融機関のローンを組んだ場合、フラット35の金利よりは高い金利が適用されますが、9割部分のフラット35の金利が安く抑えられるため、総返済額は少なく済ませられることがあります。
「フラット35 S」って何?
フラット35は性能の高い住宅の普及を目指しているため、融資の条件として住宅の耐熱性や耐久性に一定の技術基準が定められています。
このフラット35の基準を満たした上で、さらに長期優良住宅、耐震性、省エネルギー性などに優れた質の高い住宅の認定を受けると借入金利を一定期間引き下げた「フラット35 S」を利用できます。
フラット35 S の特徴
大きな特徴は当初5年間または10年間、借入金利を引き下げられることです。SーAやSーBなどの区分があり、住宅の性能の高さにより引下げポイントが加算されます。
団信保険料が金利に含まれる
住宅ローンを借りる際、借りた本人が亡くなった場合にローンが完済になる生命保険(団信保険)に加入します。
民間金融機関は団信加入が必須条件
民間金融機関の住宅ローンでは団信保険の保険料は金利に組み込まれています。
また、住宅ローンでは団信保険への加入が必須となっているため、持病があり生命保険に加入出来ない場合には審査が通過しないことになります。
フラット35は団信加入が任意
一方、フラット35の場合は団信保険への加入は任意となっています。団信保険に加入しなくても住宅ローンが組めるのです。
従来のフラット35は団信保険料を毎月の返済額とは別に、年払いで支払う必要がありました。
しかしながら、2017年10月からは民間金融機関の住宅ローンと同様に団信保険料が金利に含まれることになりました。
団信保険には健康状態の告知診査があり、持病の関係でフラット35の団信保険に加入出来ない場合には、表示金利から0.2%を差し引き、団信保険無しとして融資を受けることができます。
この場合、債務者に万が一のことがあった際はローンの債務も相続の対象となりますので、法定相続人となる奥様やお子様、両親とよく話し合って話を進めるべきでしょう。
フラット35は保証料が不要
民間金融機関の住宅ローンと、公的住宅ローンのフラット35の違いはまだあります。
民間金融機関の保証料とは
民間住宅ローンの場合、返済不能の事態に備え、契約者が保証料を支払い保証会社にリスクを肩代わりしてもらうケースが一般的です。契約者は、そのための保証料を支払う必要があります。
注意点として契約者が返済不能になった場合、保証会社は金融機関に残債を支払いますが、保証会社は契約者に返済を求めてきます。
返済する相手が金融機関から保証会社に変わるだけのことで保証料を支払ったからと言って返済免除になる訳ではありません。
保証料は借入額と借入期間によって計算されますが、契約者の職業が公務員や上場企業のサラリーマン等では保証料は低く、逆に事業の継続性や収入が不安定な方は保証料が高くなるということがあります。
フラット35は保証料不要
一方、フラット35は保証料が必要ありません。
収入が不安定になりがちな職種の方や、売上高が変動する自営業の方などもフラット35には保証料は不要です。
フラット35の年収要件
フラット35は取扱い金融機関で金利や融資事務手数料が異なります。
但し、年収から算出する借入可能額や借入期間、収入合算者の規程等は統一されています。
借入をする人(主債務者)1人で申し込む場合と、配偶者等の収入合算者を1人追加して申し込む場合があります。
収入合算者は配偶者や親、子供等のうち1人だけが対象となります。また婚約者や内縁関係にある方でも収入合算できます。収入合算者は「連帯債務者」になります。
フラット35の場合、借入可能額の審査基準は明確化されており、年収に占める住宅ローンの返済負担率を次の2つに分けています。
年収400万円未満
年収(または収入合算後の年収)が400万円未満の場合、住宅ローンの返済の負担率は30%以下となります。
年収400万円以上
年収(または収入合算後の年収)が400万円以上の場合、住宅ローンの返済負担率は35%以下となります。
ただし、上記の借入可能額につきまして自動車ローンや教育ローン、カードローン等、他の借入がある場合にはその分借入可能額が少なくなります。
もし、借入申込額を年収基準の満額迄確保したい場合は、既存の借入を住宅ローンの融資前までに一括返済する事で可能となります。
フラット35の審査は1年間の年収
フラット35の場合、民間金融機関と異なるのは審査する年収が前年1年間のみである点が挙げられます。
継続的な収入が見込まれる必要はありますが、いくら融資が可能なのかは前年の年収を返済比率の計算式に当てはめて計算しますので、自身でも資金計画が立てやすいと言えます。
また、転職して間もない方などは、転職後の給与証明などをもとにした「割戻し計算」での審査も可能です。
全期間金利変動がない安心感
全期間固定金利の公的ローンの「フラット35」は融資時に金利が決定して返済完了まで変動することがありません。変動金利商品のように、将来金利が上昇するリスクがないため、返済についての見通しがつきやすい借入方法です。また、民間金融機関よりも借入可能額が多めに確保でき、保証料が不要で、団信保険加入は任意となっています。
住宅ローンは長期にわたって返済してゆくことになるため、それぞれのライフスタイルに合った借入方法を検討することが大事です。